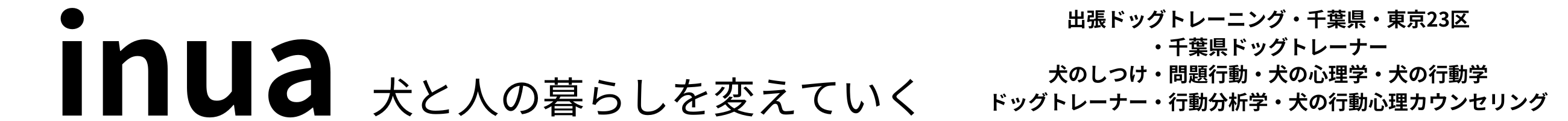こんにちは。
千葉で行動分析学を活用した犬のしつけ・トレーニングをしている
inua ドッグトレーナーの佐藤です。
「行動」の枠組みを知っていますか?
犬のしつけやトレーニングに関心のある方なら、
「行動」という言葉は日常的に耳にしますよね。
でも…
「行動」って、そもそもどういう種類があるのか
改めて考えたことはありますか?
今回は、Pool T.B.氏の1988年の論文で提唱された定義をもとに、
犬の行動の理解を深めていきましょう。
🐾 犬の行動は大きく4つに分けられる
1️⃣ 自然な行動(Natural Behavior)
野生で通常見られる行動。
例:狩り、巣作り、仲間との交流、警戒吠えなど。
これは犬の本能に根ざした、生きるための行動です。
家庭犬もこの本能を持ち続けています。
2️⃣ 不自然な行動(Unnatural Behavior)
野生では見られない行動。
ネガティブな意味ではなく、人と暮らす環境で必要な行動も含まれます。
例:
- 診察やグルーミング時の協力
- 家の中で静かに過ごす
- 公共の場で落ち着いている
人間社会で安全に暮らすために、犬が身につける行動です。
3️⃣ 正常行動(Normal Behavior)
自然な行動と不自然な行動の両方を含む、健全な行動。
例:
- 仲間や家族との遊び
- 食事を楽しむ
- 新しい場所で探索する
これらは、犬の心身の健康や生活の質(QOL)を高めます。
4️⃣ 異常行動(Abnormal Behavior)
野生ではほとんど見られず、生存や幸福に貢献しない行動。
特に「常同行動(stereotypy)」は動物福祉の観点で重要です。
常同行動とは、目的や機能がないのに繰り返される動作のこと。
例:
- 同じ場所をぐるぐる回る
- 同じ部位をしつこく舐める
⚠️ 動物福祉の視点
常同行動は、慢性的なストレスや刺激不足、
不適切な環境、または健康問題のサインかもしれません。
放置せず、獣医師や行動の専門家に相談しましょう。
僕たちと暮らす犬の特別な環境
家庭犬は、野生で必要とされる「自然な行動」が制限される一方、
「不自然な行動」を多く求められる環境に暮らしています。
これは、飢えや病気のリスクを避けられるという大きなメリットがある一方で、
本来の犬らしい行動が「問題行動」とされやすいという側面もあります。
「問題行動」とは何か?
今回、定義の中に「問題行動」という言葉はありません。
僕たちが「問題行動」と呼ぶもの――
例えば「過剰な吠え」「攻撃的な行動」「リードの引っ張り」――
これは犬にとっては自然な行動、
もしくは環境に適応しようとした結果である可能性があります。
つまり「問題行動」とは、
人間にとって望ましくない行動のことなのです。
それでもトレーニングが必要な理由
犬が安全で快適に人間社会で暮らすためには、
一定のルールやスキルを身につける必要があります。
そのため、行動の背景を理解しながら、適切にトレーニングすることが重要です。
まとめ
- 犬の行動は4つのカテゴリーに分類できる
- 「問題行動」は人間の価値観でつけられた言葉
- 犬らしさを尊重しつつ、人と暮らすための行動も必要
🐕 愛犬が犬らしく、かつ安全に暮らせる環境づくり
それが飼い主の大切な役目です。
📩 [無料相談]
「愛犬の行動が気になる」「問題行動の背景を知りたい」
そんな時はお気軽にご相談ください。
📩 [無料相談]