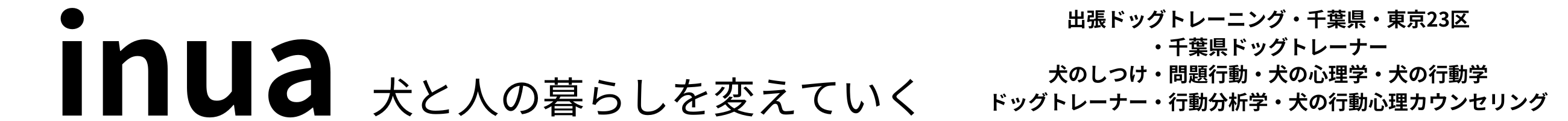こんにちは!千葉県で犬のしつけトレーニングをしている、inuaの佐藤です。
「散歩中、他の犬を見ると急に吠える・引っ張る…」
こんな時、それはリアクティビティ(過剰反応)かもしれません。

この記事では、
1️⃣ そもそもリアクティビティとは?
2️⃣ どうして起きるの?
3️⃣ 今日からできる予防・対応の工夫
をわかりやすくお伝えします。
リアクティビティとは?
犬が特定の刺激(他の犬、人、自転車、音など)に強く反応しすぎてしまうことをいいます。
こんな行動はありませんか?
- 激しく吠える
- 唸る
- リードを強く引っ張る
- 飛びかかろうとする
- 逆に固まって動けなくなる
これは「性格が悪い」わけではなく、感情や経験の影響で起こるものです。
なぜ起きるの?
主な理由は次の4つです👇
🧊 怖い・不安
- 子犬の頃に十分に社会化されていない
- 過去に嫌な経験がある
- 見慣れないものにびっくり
→ 吠えて相手を遠ざけようとすることも。
🔥 行きたいのに行けない(イライラ)
- 他の犬と挨拶したいのに近づけない
- リードや柵で動きが止められる
→ 興奮して吠えたりジャンプしたり。
🛡 守る気持ち
- 自分のテリトリー・大切なもの・飼い主さんを守ろうとしている。
📚 学習してしまった
- 吠えたら相手がいなくなった
- 飼い主がかけつけてくれた
→ 「吠えればうまくいく」と覚えた。
※ 体調や痛みがあると反応が強くなることもあります。突然、反応が出るようになった等、気になるときはまず動物病院でチェックを。
トリガーと「反応の限界ライン」を知る
トリガー=反応するきっかけ。
例:大型犬、黒い服の人、スケボーの音など。
反応の限界ライン(閾値)=まだ落ち着いていられるギリギリの距離や状況。
例:20mなら平気→10mで吠え始める。
👀 こんなサインが出たら限界が近いかも
- 舌をペロッと舐める
- 動きが止まる
- 相手をじっと見る
- 耳が後ろになる
- 身体中に力が入っている
今日からできる工夫
改善のための一歩は、吠える機会をできるだけなくすこと。
- 距離を保つ
吠えそうになる前に大きく回避。 - 視界を切る
車や植木の陰を通って相手を見せない。 - 落ち着いたら褒める
静かに通り過ぎられたら、その場でおやつや優しい声かけ。
まとめ
リアクティビティは、犬の感情や経験が関係しています。
原因ときっかけを知れば、吠える前に防ぐことができます。
🐾 次の一歩
もし「うちの子もそうかも」と思ったら、まずはトリガーと反応が始まる距離を把握することから始めてみましょう。
- 📞 「これって改善できるの?」と感じたら、初回相談(オンライン可)へ
- 📖 次の記事:「【犬の吠え・興奮】リアクティビティ(過剰反応)改善の3つの基本原理と家庭トレーニング」へ進む