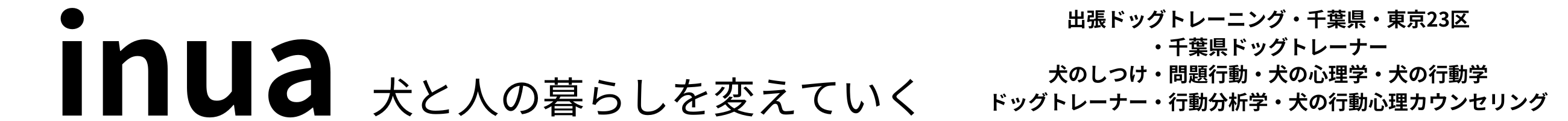こんにちは!千葉県で犬のしつけトレーニングをしている、inuaの佐藤です。
前回は、犬の「リアクティビティ(過剰反応)」の原因やトリガー、反応の限界ライン(閾値)について解説しました。
📖 前回の記事を読む
今回は、リアクティビティを罰ではなくポジティブに改善する3つの基本原理と、家庭でできる基礎トレーニングをご紹介します。
この記事を読むと、
- 吠え・興奮を防ぐための「考え方」がわかる
- 家でできる練習が見つかる
- 散歩で落ち着いて過ごせる第一歩が踏み出せます
1️⃣ 陽性強化(Positive Reinforcement)
犬が落ち着いた行動をしたら、その直後にご褒美を与えて「これが正解だよ」と教えます。
例:他犬を見ても吠えなかった → 1秒以内におやつ。
💡 避けたいこと:チョークチェーンや大声の叱責は恐怖心を増やすだけで逆効果です。
2️⃣ 脱感作+拮抗条件づけ
- 脱感作:吠えずにいられる距離から少しずつ慣らすこと。
- 拮抗条件づけ:苦手なものが見えたら特別なおやつを与え、「嫌なもの=良いこと」に近づけていく。
💡 ポイント:必ず吠えない距離から始める。怖がらせる「無理な慣らしすぎ(フラッディング)」はNG。
3️⃣ 管理(Management)
反応しやすい場面を避ける工夫です。
- 静かな時間帯に散歩
- 道を変える
- 車や植木で視界を遮る
これは「逃げ」ではなく、安全に練習を進めるための必須ステップです。
家でできる基礎トレーニング
これらは、リアクティビティーの反応改善トレーニングに必要な前提となるスキルです。
1. アイコンタクト
名前を呼び、目が合ったら即ご褒美。慣れたら「見て」の合図でできるように。
2. マテ
短時間から始め、徐々に時間・距離を延ばす。成功したら必ず褒めて解放。
3. ターゲットタッチ(鼻先タッチ)
犬の意識をトリガーから切り替え、飼い主の手や特定の物に集中させる。
4. 緊急Uターン
声の合図とおやつで180度方向転換。予期せぬ遭遇時に有効。
まとめと次のステップ
リアクティビティ改善には「陽性強化」「脱感作+拮抗条件づけ」「管理」が基本。
次回は、これらを散歩でどう実践するか、具体的なテクニックを解説します。