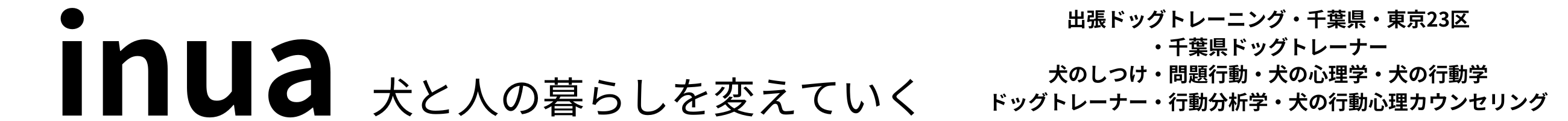こんにちは!千葉県で犬のしつけトレーニングをしている、inuaの佐藤です。
この記事はシリーズ最終回。
📖 第1回:原因と向き合い方
📖 第2回:改善の基本原理と家庭スキル
今日は、実際の散歩で役立つ具体的テクニックと、改善を続けるための心構えをご紹介します。
この記事を読むと、
- 吠え・興奮を減らす安全な歩き方がわかる
- 犬と一緒に落ち着いて通過できる方法が身につく
- 続けられるためのマインドが整う

散歩中の実践テクニック
🧍♂️ ハンドラー(飼い主)の態度
- 落ち着いて行動:肩の力を抜き、堂々と前を向く。
- 過剰な警戒はNG:必要以上にキョロキョロすると犬も不安になる。
この飼い主の行動が繰り返されると、犬は何か嫌なこと・警戒しなきゃいけないことがあると予測するようになります。
🦮 リード操作
- U字またはJ字のゆるみを保つ。
- 急な引きは避ける(痛み・恐怖で悪化)。
🎙 声の使い分け
- 基本は穏やかな声。
- 叱責は恐怖心を強めるので逆効果。
👀 観察力を磨く
- 早期サイン(舌なめずり・あくび・硬直)を見逃さない。
- 犬の視線や体の向きでトリガーを察知。
↩️ 距離と回避
- 閾値を超える前にUターン・道を変える・遮蔽物利用。
- 安全距離は犬や状況で変わる。
🎯 落ち着いた行動の強化
- 1〜2秒以内に褒めてご褒美。
- 強化する例:吠えずに通過/トリガー後のアイコンタクト/ブルブルで切り替え。
👋 注目キュー&ターゲットタッチ
- 「見て」で飼い主に注目→ご褒美。
- ターゲットタッチ:手や物に鼻先でタッチさせて意識を切り替える。すれ違い時や方向転換に有効。
成功のためのマインドセット
- 一貫性:関わる全員が同じ方法で対応。
- 忍耐:小さな進歩を認める。三歩進んで二歩下がることもある。
反応性のトレーニングには時間がかかります。
しかし、きちんとした手順を踏んで取り組めば、確実に改善していきます。
飼い主(自分)ケアも大切
- (たまには)散歩を短く/苦手な場所を避ける/室内遊びで代替。
- 仲間や専門家に相談して負担を軽減。一人で抱え込んじゃダメ。
まとめと次の一歩
リアクティビティ改善は「原因理解+家庭スキル+実践テクニック+心構え」の積み重ね。
焦らず続ければ、必ず散歩はもっと楽しくなるはずです。