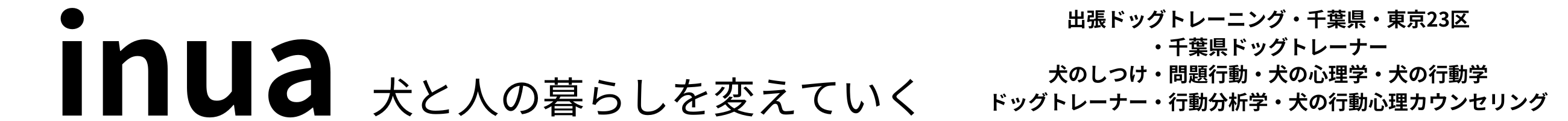こんにちは。
千葉県で犬の行動科学に基づいたしつけ・トレーニングを行っている
inuaオーナーの佐藤です。
🐾 この記事でわかること
- 犬の問題行動が続く本当の理由
- 行動の「4つの機能(目的)」とは何か
- 今日からできる観察と対処のヒント
「うちの子、なんでこんなことするの?」
愛犬との暮らしは、たくさんの喜びと癒しをくれます。
でも時には…
- 人や他の犬に吠える
- 噛もうとする
- トイレをなかなか覚えない
- お気に入りをボロボロにする
- 散歩でグイグイ引っ張る
こんな行動に、困ってしまうこともありますよね。
犬の行動は「環境」がつくる
僕たち人間を含め、動物の行動を理解する上で重要なのは、
「行動」と「環境」の関係です。
もし同じ行動が何度も繰り返されているなら…
その行動は犬に何らかのメリット(有益な結果)をもたらしている可能性が高いのです。
犬の問題行動に共通する「4つの機能」
これは、子どもの行動支援で使われる考え方ですが、犬にも当てはまります。
1:物事の獲得
欲しいものを手に入れるための行動です。
例:吠えたり飛びつくたびに、かまってもらえる・おやつがもらえる。
📌 ポイント:結果的に「望むものを得られる」と、行動は続きます。
2:課題(嫌なこと)からの逃避・回避
不快や恐怖から逃れるための行動です。
例:吠えることで、苦手な犬を遠ざけられる。
📌 ポイント:嫌な刺激がなくなる経験は、行動を強化します。
3:注目の獲得
飼い主さんの関心を引くための行動です。
例:いたずらして叱られる=注目してもらえたと感じる。
📌 ポイント:「叱る」も犬にとっては注目になる場合があります。
4:感覚刺激を得る
単に刺激を楽しむ行動です。
例:ボールを追いかける、穴を掘る、何かを噛む。
📌 ポイント:繰り返すうちに行動自体が快感になりやすいです。
なぜ理解することが大切なのか
この4つの機能を知ることで、
「うちの子は困らせたくてやっているわけじゃない」
と理解できます。
これは、飼い主さんの心の余裕にもつながります。
今日からできる行動観察のヒント
- 問題行動の直前に何があったか(先行事象)をメモする
- その行動の後に何が起きたか(後続事象)を書き出す
- 繰り返し出てくるパターンを見つける
まとめ
行動の背後にある目的を知れば、対処の方向性が見えてきます。
大切なのは「なくすこと」ではなく、
愛犬が困らなくても済む環境と、望ましい行動を育てることです。
もし改善の方法に迷ったら、ぜひお気軽にご相談ください。
あなたと愛犬に合ったアプローチを一緒に考えます。