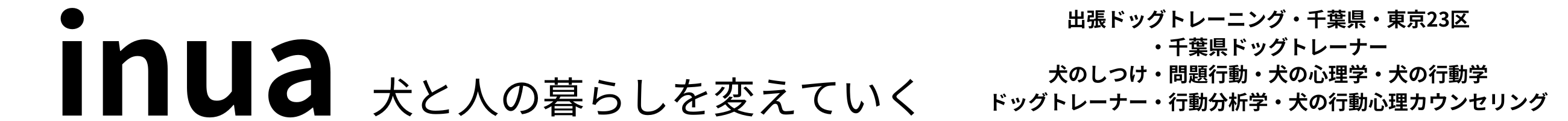「前を歩かせると、犬にナメられる」って本当?
こんにちは。
千葉県で犬の行動トレーニングを行っている、inuaオーナーの佐藤です。
こんな声を聞いたことはありませんか?
「犬が前を歩くと、主従関係が崩れるよ」
「リーダーウォークをしなきゃダメ」
「犬をボスにしないように、絶対に後ろを歩かせて」
これはかつて主流だった“しつけ論”ですが、
現在では科学的に誤りだと証明されている考え方です。
今回は、「犬が前を歩く=支配的」という誤解と、
行動科学に基づいた正しい散歩の考え方について、わかりやすく解説します。
💡「支配性理論」は、もう古い
このような主張の根拠となっていたのが、“支配性理論”と呼ばれる考え方です。
これはかつてオオカミの群れ行動を観察して生まれた理論で、
「群れの中でボスが支配しているように、犬も人間のボスの座を狙っている」とされていました。
そのため、
- 犬に主導権を握らせるな
- 飼い主がボスとして振る舞え
- 常にリーダーの立場を示すことが重要
…といったしつけ方が広まりました。
でも実は、この理論は間違いでした
1990年代後半、動物行動学の研究が進み、
この理論の元になった観察が誤解だったことが明らかになります。
- そもそも研究対象のオオカミは「人為的に集められた群れ」で、自然な群れではなかった
- 自然界のオオカミは“家族単位”で暮らし、上下関係ではなく協調で成り立っている
- 犬はオオカミとは別の進化をたどっており、同じように扱うのは不適切
これを受けて、支配性理論に基づいた「犬は常に支配しようとする」という考えは、
行動科学の世界ではすでに否定されています。
🐕 犬が前を歩く=支配してる、ではない
では、なぜ犬が前を歩くのか?
答えはシンプルです。
- そのほうが歩きやすいし、楽しい
- 気になる場所を、早く確認したい
犬は元々、探索を好み、においで世界を把握します。
前を歩くことで、より多くの刺激を得られるからそうしているだけなんです。
それは「支配」ではなく、犬らしい自然な行動です。
本当に注意すべきは「安全性」と「意思疎通」
もちろん、どんな状況でも“前を歩かせればOK”というわけではありません。
以下のようなケースでは注意が必要です。
- リードを強く引っ張ってしまい、飼い主との負担が大きい
- 他の犬や人に突然突進してしまう
- 興奮状態で指示が届かない
このような場合は、飼い主が安全をコントロールする責任があります。
ポイントは、「誰が前を歩くか」ではなく、
散歩中にどれだけお互いに安心して歩けるかということです。
正しい散歩とは「犬の欲求を満たす時間」
良い散歩には、しつけ効果だけでなく以下のようなメリットがあります。
- 情緒の安定(=問題行動の予防につながる)
- 嗅覚による脳の刺激(=認知機能の向上)
- 飼い主とのポジティブな関係構築
つまり、散歩は犬の心と行動を整える“栄養”のようなもの。
前を歩かせる・後ろを歩かせるといった表面的なルールに縛られるのではなく、
犬の気持ちに寄り添いながら、一緒に心地よく歩けることが何より大切です。
まとめ|支配性よりも、安全と信頼を大切に
「犬にナメられているかも…」
→ その心配、ほとんどの場合必要ありません。
「前を歩くとボスになろうとしてる?」
→ 犬はそんなこと考えていません。
科学が進んだ今、私たちは犬の行動を“力”ではなく“理解”で導けます。
散歩は、あなたと愛犬が同じ方向を見て歩ける大切な時間。
間違った情報に惑わされず、今日からもっと自由で楽しい散歩にしていきましょう!
📩無料相談受付中
「散歩で引っ張りがひどくて困ってる…」
「うちの子、前を歩きたがるけど大丈夫?」
そんなお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
inuaでは、犬の行動科学にもとづいた個別アドバイスをご提供しています。
🔍よくある質問(FAQ)
Q. 本当に“前を歩かせるだけ”で悪い子になることはないんですか?
→ はい。行動科学的にもそのような根拠はありません。大切なのは「関係性」と「安全管理」です。
Q. それでも前を歩かせたくないのですが…
→ 飼い主さんが歩きやすさや安心感を重視したい場合はOKです。「どう歩かせるか」は家庭ごとに違って構いません。